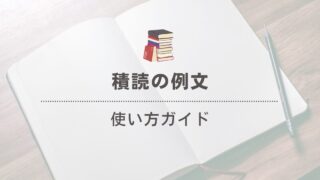PR
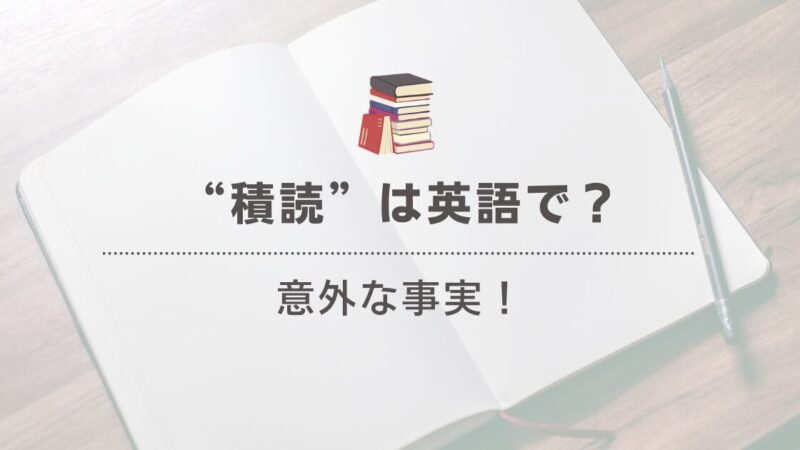
「積読(つんどく)」という言葉、最近では日本だけでなく、海外でも耳にするようになりました。
本好きの人なら一度は経験したことがある「積読」。
それは、本を買っては読まずに積んでしまう状態を指します。
この「積読」という言葉、実は英語圏でもそのまま使われることが増えているんです。
でも、英語ではどう表現するのが適切なのでしょうか?
今回は「積読」を中心に、その言語的な背景や英語表現について探っていきます。
「積読」を英語でどう表現する?
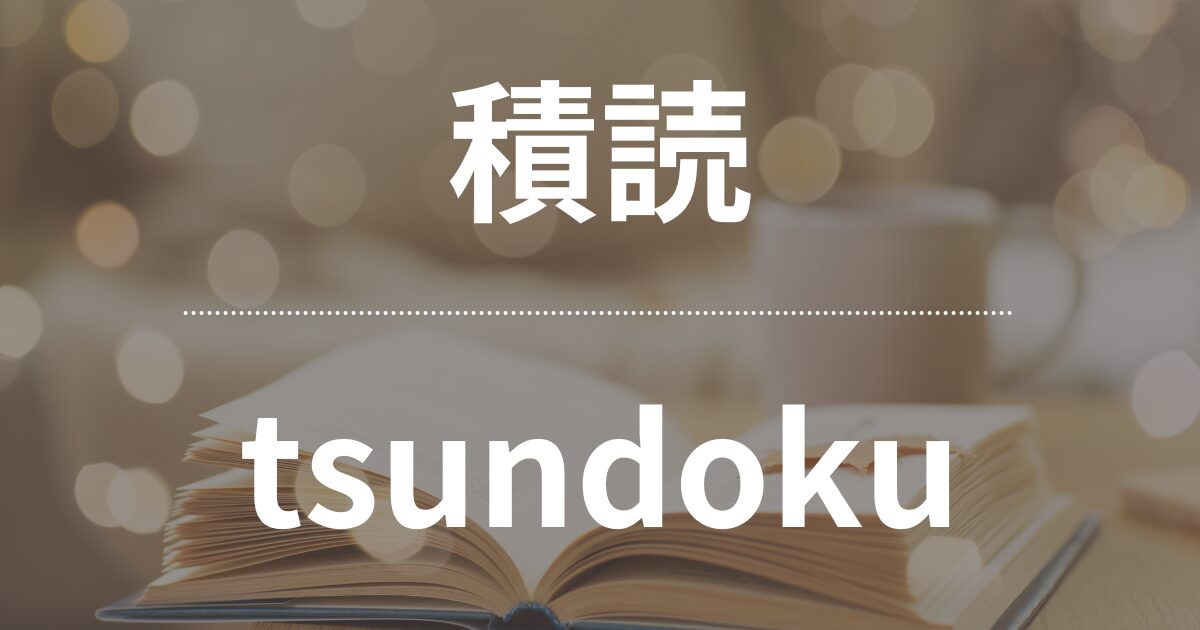
では、「積読」を英語でどう表現するかについて考えてみましょう。
実際には「積読」にぴったりの英語表現は存在しないため、いくつかの方法で言い換えることが一般的です。
日本語の例文はこちらで解説しています。
Tsundoku:そのまま英語として使われる場合
最近では、「Tsundoku」がそのまま英語として使われることが増えています。
これは、日本独特の概念をそのまま取り入れた形です。
英語圏の読書好きたちも、この言葉に魅力を感じ、積極的に使うようになっているのです。
実際に「Tsundoku」はBBCなどのメディアでも取り上げられ、世界中の人々が「積読」の魅力に触れています。
英語での使用例は以下のようになります。
- “I have a serious case of Tsundoku — I keep buying books but never get around to reading them.”
- “Do you know what Tsundoku means? It’s when you buy books and let them pile up without reading them.”
このように、「Tsundoku」は、英語の会話や文章でも徐々に定着しつつあります。
日本語の言葉がそのまま海外で使われるというのは、ある意味とても面白い現象ですね。
「積読」を説明的に言い換える方法
一般的には「Tsundoku」という言葉がまだ広く知られているわけではありません。
したがって、他の言い方を使うこともあります。
例えば、以下のような表現が使われることが多いです。
| 英語の表現 | 意味 |
|---|---|
| Books piling up unread | 読まずに積み上げられている本たち |
| Unread book collection | 読まれていない本のコレクション |
| The habit of buying books and not reading | 本を買っても読まない習慣 |
例えば、「I have a habit of letting books pile up unread.」という風に言えば、「積読してしまう」という意味が伝わります。
このように、英語では説明的に言い換える方法がよく使われます。
「積読」の言語的な背景

まず、「積読」という言葉がどのように生まれたのか、そしてそれがどのように使われているのかを見てみましょう。
この言葉には、日本語特有のニュアンスが含まれているため、他の言語で表現するのは一筋縄ではいかない部分もあります。
「積読」の語源と日本での使われ方
「積読」という言葉は、日本語の「積む(つむ)」と「読書(どくしょ)」を組み合わせた造語です。
「積む」は何かを積み上げるという意味で、「読書」はもちろん本を読むことを指します。
つまり、「積読」は「本を積んでおいて読まない」という行為を的確に表現しているのです。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 積む | 何かを積み上げる |
| 読書 | 本を読むこと |
| 積読 | 買った本を読まずに積み上げておく行為 |
日本では、この「積読」という言葉が多くの本好きに共感を呼び、日常的に使われるようになりました。
特に、時間がないけれど本を買ってしまう人にとって、この言葉はまさに「あるある」を表すものであり、自分を少しでも正当化してくれる、そんな魔法の言葉とも言えるでしょう。
積読はどこの国の言葉?
「積読」は、もちろん日本発の言葉です。
しかし、この行為自体は世界中の本好きに共通して見られるものです。
そのため、日本語の「積読」という言葉は、最近ではそのまま英語圏でも使われ始めています。
英語圏の書店や図書館で「Tsundoku」という表現を目にすることもあるかもしれません。
積読の文化的背景
・日本発の言葉だが、世界中の本好きに共通する
・日本語特有のニュアンスを含むため、多言語への翻訳は難しい
・海外でも「Tsundoku」という言葉が徐々に広まっている
このように、「積読」は日本固有の言葉でありつつ、グローバルな共感を得ている概念でもあるのです。
積読にまつわるおもしろい事実
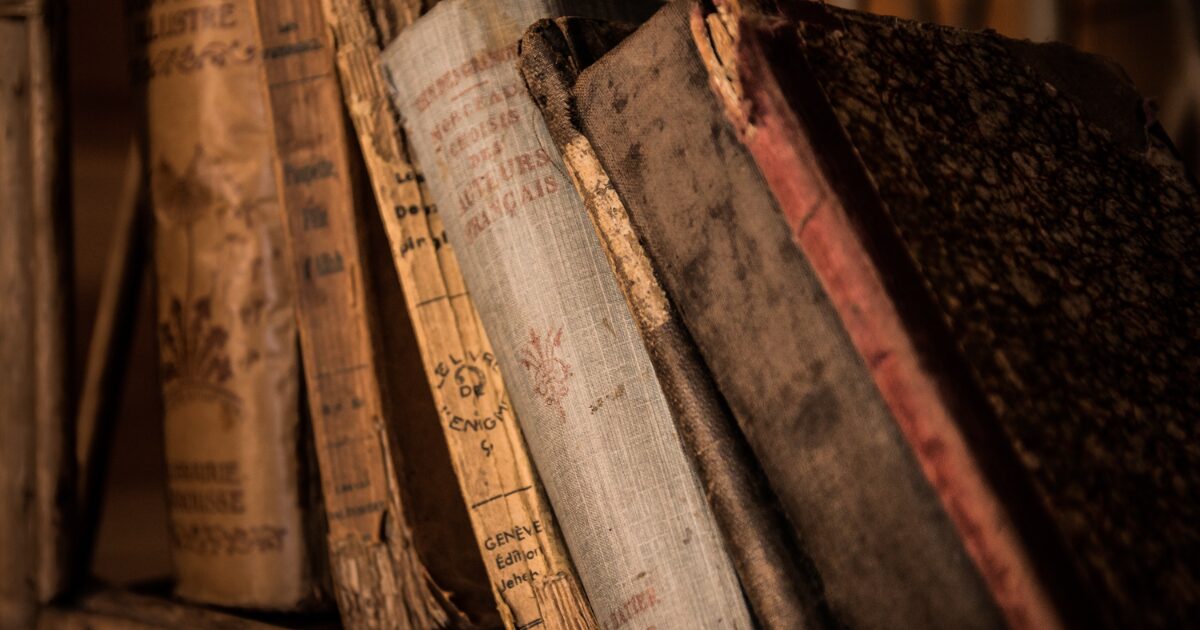
積読という言葉には、日本文化特有のユーモアと哲学が詰まっています。
ここでは、積読にまつわるいくつかの面白い事実や背景について掘り下げてみましょう。
積読は日本独特の文化?
「積読」という言葉自体は日本発祥ですが、その背後には、物を大切にし、知識を尊ぶ日本の文化が影響しているとも言われています。
日本人は古くから書物を神聖視し、知識の集積を尊んできました。
そのため、たとえ読まなくても「本を持っている」ことに価値を見出す文化が育まれてきたのです。
積読と日本文化の関連は以下のように言われていたりします。
- 知識や情報を積み重ねることに価値を感じる
- 本を所有すること自体が、教養や文化を尊ぶ姿勢を表している
- 実際に読むかどうかより、持っていることで満足感を得る
このような文化的背景が、「積読」という言葉の意味をさらに深めているのかもしれません。
海外でも積読文化は存在する?
日本特有の「積読」ですが、実際には世界中で似たような現象が見られます。
英語圏では、「book hoarding(本を溜め込む)」という言葉で表現されることもありますが、微妙にニュアンスが異なります。
積読が「読むつもりで積んでおく」行為であるのに対し、book hoardingは「本を集めて満足する」行為を意味することが多いのです。
以下は海外の積読に近い言葉です。
| Book hoarding: | 本を集めること自体が目的になっている場合 |
| TBR pile (To Be Read pile) | 読む予定の本が積み上がった山 |
| ook buying addiction | 本を買うことが習慣になっている状態 |
このように、積読に似た行為は世界中に存在するものの、日本語の「積読」には、よりポジティブで文化的なニュアンスが含まれています。
おわりに:積読は文化を超えて広がる
「積読」という言葉は、単に読まない本を積んでおく行為を表すだけでなく、知識や教養を尊ぶ姿勢、そして本への愛情を象徴しています。
そのため、この言葉は日本だけでなく、英語圏でも共感を呼び、「Tsundoku」として広まりつつあります。
BBCなどのメディアでも取り上げられたこの現象は、世界中で共感を呼んでいる証拠です。
積読という行為は、私たちの文化や心理に深く根付いていることを示していると言えるでしょう。
これからも「積読」という言葉が、世界中で共感を呼び続けることを願っています。
言葉の壁を越えて、本への愛が広がっていくのは、とても素晴らしいことです。
積読を通じて、私たちの読書習慣や文化がさらに豊かになることを期待しましょう。